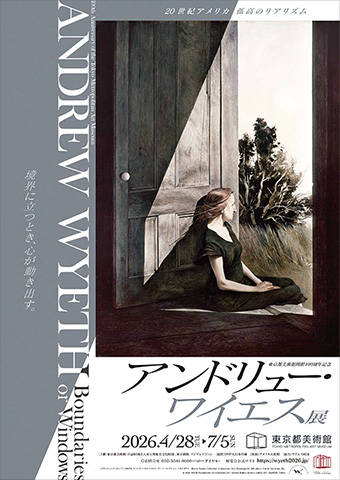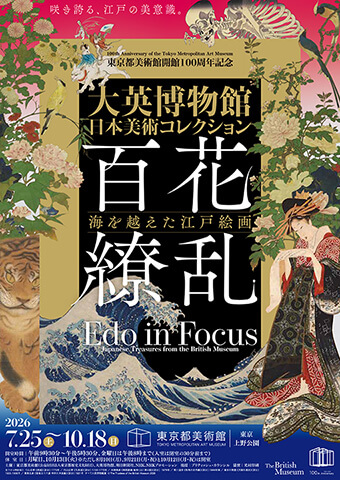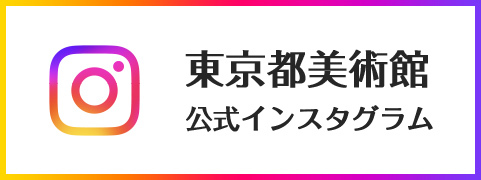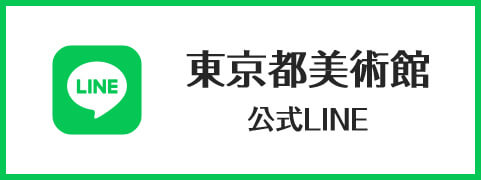本日は全館休館日です
本日の開館時間 9:30~17:30
本日の開館時間 9:30~17:30
本日の開館時間 9:30~17:30
本日の開館時間 9:30~20:00
本日の開館時間 9:30~21:00
-
2026/2/19ニュース
-
2026/2/12トピックス
-
2026/2/12募集
-
2026/2/12トピックス
-
2026/1/27トピックス
-
2026/1/27ニュース
-
2026/1/26ニュース
-
2026/1/22ニュース
-
2026/1/22トピックス
-
2025/12/4トピックス
-
2025/11/6トピックス
-
2025/11/6ニュース
-
2025/10/30トピックス
-
2025/10/23ニュース
-
2025/9/4トピックス
-
2025/8/28ニュース
-
2025/7/10トピックス
-
2025/5/22ニュース
-
2025/4/25ニュース
-
2023/7/27ニュース
もっと見る